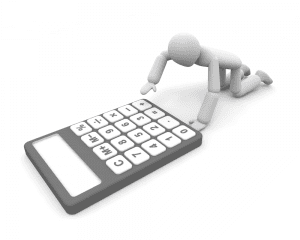ネットショップや取り扱う商品に適した配送サービスを選ぶことは大変重要です。
しかし、先に注目すべきは注文が入ってからの対応です。
理由は、配送サービスは宅配会社によって、最適化や効率化が高いレベルで実現されているからです。
そのため、まずは注文が入ってから発送までの流れを掴みましょう。
本記事では、ネットショップの受注から発送までのプロセスや、取り扱う商品に合わせた配送方法について解説します。
出荷作業が遅い…ネットショップに適した配送がわからない!という方はぜひ最後までご覧ください。
目次
ネットショップにおける配送の流れの重要性

ネットショップにおける配送の流れとは、顧客が注文した商品を正しく、早く届けるプロセスを指します。
具体的には「受注 → 在庫確認と検品 → 支払い確認 → 発送」という流れです。
ここで注目すべきは、受注 ~ 発送までの流れの迅速化、効率化です。
理由は、商品を直接注文客に届けるのは宅配業者の業務であり、ネットショップのほうで直接コントロールができません。
つまり、前述した「受注~発送」の流れをいかに効率を良くすることがネットショップが直接コントロールできる部分といえます。
注文があり次第、短時間で発送できる流れを作れれば、顧客満足度の向上とリピーターの獲得に役立つでしょう。
スムーズな配送は「またこのショップで買いたい」という気持ちを顧客に与えるからです
次章では、受注~発送までのステップをわかりやすく整理し、ネットショップ運営における流れの重要性を紹介します。
まずは、流れの全体像を把握することから始めましょう。
ネットショップにおける配送までの流れと5つのステップ

ネットショップでは、当日発送が当たり前になりつつあります。当日発送を実現するには、以下の5つのステップの迅速化が必要です。
- 受注
- 注文確認
- 在庫確認と検品
- 支払い確認
- 発送
それぞれのステップを確認していきましょう。
受注
ネットショップでユーザーが商品をカートに入れて、注文ボタンがクリックされると運営側に通知が届きます。これが最初の「受注」のステップです。
大抵のネットショップでは、受注管理システムやカートシステムが自動的に注文情報を取り込み、販売可能な在庫数を計算してくれます。
現在の在庫数から受注数を引いておくことを「在庫の引き当て」といいます。受注済みの数量を在庫数から差し引いておかないと、在庫数以上の受注をしてしまうリスクがあります。
在庫切れで受注をしてしまうと、顧客へ在庫切れの連絡をするか、入荷予定を通知する必要に迫られるでしょう。この発送の遅延や、在庫の誤認識は、顧客満足度を大きく下げるため避けないといけません。
受注と在庫の連動をリアルタイムで行う仕組みはネットショップの立ち上げ当初からあると理想的です。次は注文情報を確認するステップに入ります。
注文確認
楽天やAmazonで注文をしたら、すぐにメールボックスに「注文確認メール」を受信しているのではないでしょうか。
この自動返信機能は、多くのネットショップで導入されており、注文した後に自動的に注文内容を送る機能を備えています。メールの宛名に購入者の「○○様」と名前が自動的に差し込まれるので、購入者が注文内容を確認でき、安心感を与えやすいです。また、このステップは自動返信機能を導入するだけで完全自動化が可能です。
検品と梱包
受注と注文確認が完了したら、在庫情報を照合、保管場所から商品を取り出し(ピッキング)します。
次に、注文情報と突き合わせながら、型番・数量・サイズ・外観の傷や汚れをチェックし、破損の有無を「検品」します。商品によっては動作確認もすることになるでしょう。
検品後は、輸送中の破損を防ぐため、段ボールに梱包します。梱包は単なる保護ではなく、ショップの印象を決める重要なポイントです。注文客は梱包された状態で商品を受け取り、開封を楽しむ人も少なくありません。
この開封する際に、梱包が乱雑、粗末な印象を与えてしまうと、顧客満足度の低下やクレームになる可能性があります。
段ボールのサイズや、使用する緩衝材は商品ごとに最適化しましょう。そのためには、梱包のクオリティを一定にするため、作業マニュアルの整備が必要です。
支払い確認
支払いがクレジットカードや電子マネー決済の場合は、Web上ですぐに支払いの有無を確認できます。しかし、以下のような支払いの場合は別途対応が必要です。
- 銀行振込
- コンビニ払い
- 代金引換
上の2つは、入金が完了したか口座を確認してから発送しないといけません。代金引換の場合は、発送後の着払いなので商品の受け取りの際に代金が回収され、配送会社より振り込みがあります。いずれにしても、支払い完了または方法を確認してから商品発送のステップになります。
商品発送
梱包した商品を配送会社に集荷依頼をして荷物を引き渡します。
配送会社としては、ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便が主要な宅配会社です。配送ラベルを自動発行するシステムを導入すれば、作業効率が格段に向上するでしょう。
発送後は「発送完了」のお知らせをユーザーに送信します。追跡番号があれば、発送完了のお知らせに明記して通知しましょう。
商品が無事に届いた後も、商品が破損していた場合や返品を希望するユーザーに対して迅速かつ丁寧な対応をしましょう。
商品到着後のフォローや、返品対応を丁寧に対応することで、顧客の信頼を得られ、リピーター獲得につながるからです。
このように、全体の流れの中で配送会社が占めているのは最後のステップだけです。重要なポジションを担っているものの、フォローまで含めれば多くのステップはネットショップ側で改善できる部分があるのではないでしょうか。
自社のネットショップに合う配送サービス3つの選び方

ここからはネットショップに合う配送サービスを以下の3つの選び方で紹介します。
- 人気
- 料金
- サービス内容(追跡機能と補償の充実度合)
大抵の場合、配送サービスは2つ目の料金で選ぶ場合が多いでしょう。しかし、受け取る顧客側から考えた場合は違った選択肢があるかもしれません。
人気
一般的に使われている配送サービスのほうが、受け取るユーザーも再配達依頼や受け取り方法が決まっているため安心です。反対に、あまり使われていない配送サービスだと、再配達の仕方やいつもの受け取り方法が指定できないなど不便な場合があります。
場合によっては、受け取りまでに手間と時間がかかり満足度を損なうかもしれません。そのため、人気のある配送方法を選ぶほうが受け取り側にとって使い勝手が良いといえるでしょう。
国土交通省の令和6年度 宅配便(トラック)取扱個数の上位を占めるのは以下の3社です。
| 事業者 | サービス名 | 構成比 |
|---|---|---|
| ヤマト運輸 | 宅急便 | 47.2% |
| 佐川急便 | 飛脚宅配便 | 25.8% |
| 日本郵便 | ゆうパック | 22.2% |
これ以降に福山通運と西濃運輸が続きます。
したがって、ヤマト運輸の宅急便を利用すれば大抵のユーザーにはなじみのある方法で配送されるため、安心といえるのではないでしょうか。
料金
配送を料金で選ぶ場合、候補となるのはメール便、または宅配便になるでしょう。メール便は、全国一律料金で低コストでの配送が可能であるものの、小型の商品でないとサイズオーバーとなって利用できません。対して、宅配便の配送コストはメール便より高めですが、サイズごとに料金が細かく区分けされています。
大抵のネットショップの配送方法は、メール便、宅配便のどちらかです。小物や少量の注文の場合は、メール便を選び、重量やサイズがオーバーした場合は宅配便を使うのが一般的な方法になるでしょう。
ただし、メール便と宅配便では、追跡機能や補償額にも違いがあります。
詳しくは次で解説します。
サービス内容(追跡機能と補償の充実度合)
配送のサービス内容(追跡機能有無と補償の充実度合)で発送方法を選ぶことも大切です。
基本的な宅配便は、追跡機能で荷物の位置を詳細に把握できます。また、輸送中に破損や紛失、盗難といったトラブルが起きても、ある程度まで配送会社が補償してくれます。
メール便にも追跡や補償はあるものの限定的です。特に、高額商品を扱う場合は、メール便で送れるサイズであっても宅配便を利用するべきでしょう。
まとめると、追跡や補償によるサービスを優先して配送方法を選べば、万が一のトラブルの際にもネットショップと顧客の両方が安心です。
通販の配送料無料のからくり:余談

ネットショップでは商品を配送して届けるため、確実に送料が発生します。しかし、チラシやFaxを使う通販では「送料無料」は当たり前でした。これは以下の方法で送料を無料にしているケースが多いです。
- 送料込みの価格で提供している
- 利益率の高い商品で配送料をまかなう
「送料無料」はユーザーにとっては魅力的です。しかし、送料を店舗側が負担すると利益が圧迫されます。そこで、送料を無料にしつつ、利益を確保するため以下のような方法が考えられます。
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| 一定金額以上の購入で送料無料 | 客単価を上げて送料負担を軽減する |
| 送料込みの価格設定 | あらかじめ商品価格に送料を組み込む |
| 配送会社と割引料金で契約 | 毎回一定量の出荷を行うことで運賃を抑える |
送料無料は「顧客満足度」と「利益率」のバランスをどう取るかが鍵となります。3つのうち2つを組み合わせると利益率を確保しやすくなるでしょう。
商品ごとのおすすめのネットショップ配送サービス

配送サービス選びは「どの配送会社が安いか」だけではなく、「商品特性に合った手段を選ぶ」ことも重要です。
この章では、代表的な商品カテゴリーごとに適した配送サービスを4つ解説します。商品に応じた配送サービスを選ぶことは、ネットショップにとって「隠れたおもてなし」になるでしょう。
書籍・雑貨などの小物 → 日本郵便のクリックポスト・ゆうパケット
厚み3cm以下、重さ1kg未満の小型商品の発送には、クリックポストやゆうパケットが適しています。
しかも、送料は全国一律で200 〜 400円台で抑えられます(2025年9月時点)。
ポスト投函なので受取側の手間も少なく、顧客満足度も高いです。
ただし、小物であっても破損しやすい物や高価なものは避けてください。
前述したように、宅配便に比べて補償が少ないからです。
アパレル商品 → ヤマト運輸の宅急便コンパクト
薄手の衣類は、宅急便コンパクトがちょうど良い選択肢となるでしょう。専用BOXがあるため、型崩れを防ぎつつ、割安な料金で配送コストを抑えられます。
また、返品や交換が多いアパレル用品では、追跡機能と配達までの発送スピードが顧客満足度にプラスに働きます。
ただし、枚数が複数ある、かさばる場合は、サイズオーバーとなるため、通常の宅急便にしましょう。
無理やり詰め込むと衣類の型が崩れたり、靴であれば折り目がついたりして、クレームになるかもしれないからです。
生鮮食品・冷凍食品 → ヤマト運輸のクール宅急便
鮮度が命の商品はクール便一択です。冷蔵・冷凍の温度帯が選べ、魚や肉などのチルド食品やアイスクリームやケーキなどのスイーツの配送にも対応できます。
消費期限の短い商品ほど配送スピードが重要になるため、大手のヤマト運輸を選ぶのが妥当でしょう。
ときどき送料を抑えるために発泡スチロールに食品とドライアイスを入れて、常温便で送ろうと考える人がいますが…やめましょう。確実にクレームになります。
高額商品・重量物 → 佐川急便の飛脚宅配便
高額商品や重量物の配送には、佐川急便のほうが補償額を広げることができるため、飛脚宅配便がおすすめです。
別途保険料を支払うことで運送保険の加入ができ、最大で100万円までカバーできます。対して、ヤマト運輸の宅急便の補償金額は、宅急便1個につき30万円(税込み)までです。
また、重量物に関しても佐川急便も飛脚ラージサイズ宅配便であれば50kgまで発送可能であり、大型の家具は「飛脚大型家具・家電設置便」も提供しています。
以上のことから、ブランド物や家電などの商品は、補償や重量物への取り扱いが整っている佐川急便が適しています。
他の商品とは異なる場合は、リスクを減らすため手厚い補償は必須といえるでしょう。
適した配送サービスを選んでネットショップの流れを効率化:まとめ

ネットショップにとって配送は、顧客満足度に大きな影響を与える重要な要素です。しかし、直接対応できる訳ではないため、注文が入ってから迅速に発送するという点も忘れてはいけません。
小規模であれば、マニュアルを作成して手作業でも対応できます。しかし、ある程度の規模で運営する場合、受注から発送までのステップを効率化していく必要があります。
ムダのない出荷体制を構築したい!ネットショップに適した配送の選び方がわからない!という方は当社にお気軽にご相談ください。扱う商品や予算に合った最適な配送方法や保管方法についてご紹介します。
 0120-612-675
0120-612-675