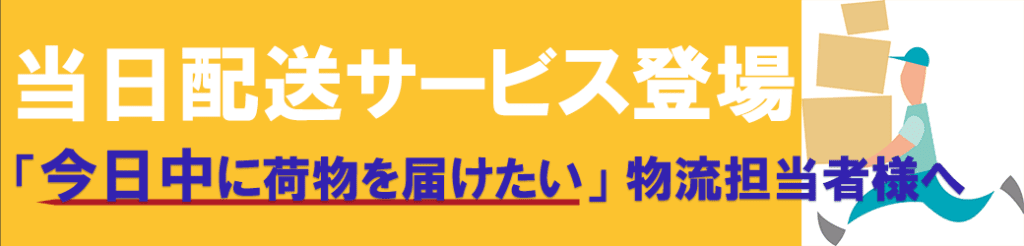物流ABCは物流コストを管理する手法として、物流業界で重視されている考え方ですが、実際にはすべての物流企業で採用されているわけではありません。しかし、経営の流れなどを明確化して経費などを節約するためには物流ABCは重要であり、少しでも早い段階での導入がおすすめです。
導入するためにはコストの計算方法や物流ABCをどのように活用すれば良いかについて理解しなければいけません。今回は物流ABCの具体的な流れやメリット・デメリットについて紹介していくので参考にしてみてください。
物流担当者が知っておくべき!アウトソーシングで期待できる導入効果とは
目次
物流ABCとは?
ABC【Activity Based Costing】とは、活動基準原価計算の意味です。
物流における原価を計算することで、それぞれの段階での原価を把握してどのような工夫をすれば良いかの指標になります。昔から同じ行程で作業をしている企業などでは自分たちで考えているよりも、無駄なコストが発生している可能性が高いです。そういった無駄なコストを把握しないまま企業活動を続けてしまうと年間を通して考えれば、無駄になっているコストは想定よりも大きい恐れもあります。
物流ABCで物流コストが把握できる
物流コストは企業経営において必要不可欠になるケースが多いことから、正確に把握できれば企業の問題点などもわかります。そのため、物流コスト全体を大きく削減するためには、日々の物流コストの流れを把握し、どのようにコストを削減するかが重要です。物流コストは具体的に把握されることが少なく、長い間同じ物流プロセスを継続しているケースでは、無駄なコストが多く発生する傾向があります。
物流ABCでは、段階ごとの原価を計算するため、どこの段階で原価が高いのか、原価を下げるためになにか工夫ができるかの判断が容易になります。段階別にコストを計算すると、予想以上に無駄なコストが多いということはよくあることで、無駄な部分を洗い出して減らすことができれば、物流のコストを削減することができるのです。物流のABCで物流の流れを把握することができれば、効率的な企業活動を行うことができるようになります。
物流ABCを考える際の注意点
一方で、それぞれの段階において必要なデータを収集しなければいけませんが、データ収集は一回だけで完了しません。複数回データを収集することで、各段階に必要な時間や作業数を把握し、収集したデータを分析することで無駄なコストを把握することが重要です。継続的なデータ収集が必要となることで、従業員の作業負担が増える可能性が高いため、従業員の作業負担が大きくなりすぎないように注意する必要があります。
また、各過程における原価などを計算することになりますが、コストが高い活動が実際には必要不可欠な活動であるケースも珍しくありません。計算結果を参考にして業務改善をすることが目的といえますが、他の要素なども考えながら本当に削減しなければならないかの判断が必要です。
物流ABCの計算方法
正確な数値を出すには複数のステップを踏む必要がありますが、物流の流れなどを段階的に見直すことで計算が可能です。また、各作業にかかるコストを計算し、現状の物流システムのどこにどれだけのコストが必要なのかを把握する必要があります。もしも、計算方法について把握しないまま、それぞれの作業過程で必要になるコストを算出してしまえば、本当に各過程で必要になっているコストよりも高い結果がでたり、低い結果がでたりして正確に原価については把握ができません。
具体的な物流ABCの計算方法については、以下の項目をご参照ください。
ステップ1. 目的の明確化
まず、物流コストのどの部分を削減したいのか、目的を明確にすることが大切です。
例えば、物流工程で商品を出荷するための人件費や輸送費を削減することが目的であったり、自社で保有する在庫量を削減することが目的であったりします。企業によって物流コストに関わる内容は異なるため、自社の目的を正確に把握することが重要となります。
また、一度に複数の目的を設定するのではなく、少しずつ改善していく意識で活動を行わないと、会社全体の負担が一気に増えてしまいます。特に、データ収集の分野で多くの目標を設定すると、必要なデータ量も増えてしまいます。データ収集の精度が低い場合やデータ収集に時間がかかってしまえば、それだけでも計算できるタイミングが遅くなってしまいます。
目的によって必要なデータや分析方法が異なるので、実際に物流ABCを使って物流コストを計算する前に、目的を明確にしてください。
ステップ2. 必要とされる作業を設定
作業ごとに計算する必要があるため、作業内容を設定する必要がありますが、作業内容を設定する際に、細かく作業内容を設定する必要はありません。関係者が聞いただけで具体的にイメージできるように、定期的に行われる作業のみを設定します。
例えば、定期的に行う作業としては、入荷作業、梱包作業、伝票作成、検品作業などがあります。各作業の内容を明確にし定常的に行われる作業を設定することが、最終的に物流ABCを算出するために必要です。
ステップ3. どれくらいのコストが必要になるかを理解する
どれくらいのコストが必要になるかを理解するためには、投入要素を算出する必要があります。
投入要素とは、商品を運ぶために必要な車両や燃料、物流工程にかかる人件費、棚や作業台などの設備、入荷・出荷する商品を保管する倉庫、ダンボールなどの商品梱包資材などです。
この段階では作業工程ごとに計算はせずに、物流工程でこれまで必要とされた投入要素ごとのコスト計算を行います。これまでの使用量などを正確に把握する必要があるため、過去の会計データを参照し、投入要素を正確に算出してください。
ステップ4. 作業内容ごとの原価を計算
作業内容ごとの原価を計算するための投入要素ごとに必要になったコストを計算していきますが、投入要素を設定した作業ごとにどれくらい必要にあるかについて計算をおこないます。
例えば、商品の梱包にはダンボール箱などの緩衝材が必要ですが、物流工程での人件費にはダンボール箱などの投入要素は必要ありません。各作業工程に必要な投入要素を正確に把握できれば、ようやく各作業工程の原価を把握することができます。正確に原価を把握していなければ最終的な計算が正しくならない恐れがあることから、間違いがないように確認しながら計算してください。
ステップ5. 作業内容ごとの処理量を理解する
作業内容ごとに処理量を理解して、どれくらいの量を設定するかを考えなければいけません。作業量が多くなれば必要になるコストは多くなり、単純に作業であれば処理量、伝票作成であれば伝票作成枚数などが対象になります。どれだけのコストが必要なのかが分かれば、各作業の効率や無駄なコストを把握することができるようになります。
ステップ6. 作業内容と目的の単価を計算する
作業内容と目的の単価を計算するためには、作業ごとの原価と作業ごとの処理量を把握する必要がありますが、ここまでのステップをおこなっていれば原価と処理量に関しては算出ができています。
作業と目的の最終単価を算出するためには、以下の計算式を用います。
作業内容単価=作業内容原価÷作業での処理量
上記の計算ができれば、作業の単価を導き出すことができ、作業の単価がわかれば、目的別コストも計算することができます。
目的ごとのコスト=作業内容単価×目的別処理量
上記の計算で目的ごとのコストを算出できますが、目的ごとのコストを確認してコストカットできる部分があるかについて把握してください。
算出した物流コストを参考にすれば経費削減にも貢献できる
算出した物流コストを参考にすればコスト削減に貢献できるため、物流コストは正確に算出する必要があります。しかし、物流コストを算出しただけでは物流コストは削減できないため、実際に物流コストの流れを確認し、どの部分でコストを削減すべきかを判断する必要です。ここで注意したいのは、物流コスト削減のために無理な対応をすると、従業員の負担が増えるだけでなく、安全性や正確性にも悪影響が出るおそれがあることです。自社で判断がつかない場合は、第三者の専門家に依頼して解決することをお勧めします。
まとめ
計算結果を参考にして、強引にコストカットをしてしまえばさまざまな悪影響が発生することは意識してください。物流コストを正確に把握したければステップを確実におこなわなければいけませんが、各過程においてどうすれば良いかの判断が難しければ専門家に依頼してください。
最終的にコストカットや効率化を目指しているなら、早い段階で取り組むことが求められますが、焦って各ステップでの設定や計算が不正確になってしまえば最終的な計算もずれてしまうので注意が必要です。企業活動において悪影響が出る可能性も考えながら、メリット・デメリットについても正確に把握してからの活動をしましょう。
導入事例や細かい料金体系、お問い合わせから業務開始までの流れがわかる!
自社サービスの紹介資料になります。物流業務のアウトソーシングをご検討されている方は、ぜひ一度ダウンロードください。
- 導入フローについて
- MOTOMURAの特徴
- 期待できる導入効果
- 取引実績一覧
- 基本料金体系
フォームにご記入いただくと、無料で資料がダウンロードできます。
いただいたメールアドレス宛に資料が自動送信されます。

 0120-612-675
0120-612-675